発達障がいと特別支援教育 ~小学生編
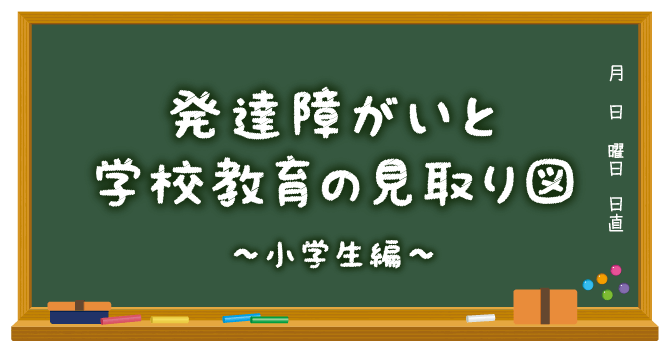
発達の遅れや特性をもつお子さんの小学校選びに悩む保護者は多いのではないでしょうか。
「学校」という場でお子さんにどの程度の支援が必要なのか、素人である親が判断するのはとても難しく、プロである医師や臨床心理士、学校の先生に言われる言葉はひとつひとつが響きます。
診断名やIQ値などから一概に決められるものではなく、担任の先生は選ぶことができないので「結局は運次第」という声もよく聞きます。
ここでは【地域の差】【学校ごとの差】【先生の差】を抜きにして、発達障がいのお子さんの小学校教育について、全体を見渡す「見取り図」になるお話をします。
「特別支援教育」ってなに?
特別支援教育とは、幼稚園、小~高校生の発達支援です。
障がいのあるお子さんひとりひとりの教育的ニーズに応じた支援に重点が置かれています。

しえんきゅう?つうきゅう?
「なかよし学級」みたいなクラスのことでしょうか?似た言葉が多くて混乱しちゃうので教えて下さい!
では、特別支援教育に関わる機関についてご説明します。
就学相談・転学相談
障がいや発達の遅れのあるお子さんに対する教育や学校選びについて、保護者が相談する事ができます。
| 対象 | 発達の遅れや障がいによって配慮が必要とされる児童・生徒 |
|---|---|
| 管轄 | 都道府県・区市町村の教育委員会 |
| 概要 | 障がいや発達に遅れ、病気や怪我を負ったお子さんに対する教育について、就学相談員による判定を受けたり保護者が相談できる場所。 保護者の要望を伝えながら、子どもにとって望ましい教育環境が整った就学先について相談できる。 |
通常学級
公立小学校の学級、障がいのある子もない子も、全ての子どもが通うことができます。
| 対象 | 全ての児童・生徒 |
|---|---|
| 管轄 | 区市町村の教育委員会 |
| 在籍学級 | 普通学級 |
| クラスごとの人数 | 40名(小学校1年は35名) |
| 概要 | 一般的な公立小学校を指す。 通常の学級も「特別支援教育」に含まれるので、通常の学級に在籍しながら「特別支援学級」や「通級による指導」に通える制度もある。 現在は通常の学級で学習を支援する「支援員」の活用も広がっている。 |
特別支援学級
小・中学校内にある障がいのある児童のための少人数学級です。
| 対象 | 知的障がい(知的障がい特別支援学級)、肢体不自由(肢体不自由特別支援学級)、病弱・身体虚弱(病弱・身体虚弱特別支援学級)、弱視(弱視特別支援学級)、難聴(難聴特別支援学級)、言語障がい(言語障がい特別支援学級)、発達障がい(自閉症・情緒障がい特別支援学級) |
|---|---|
| 管轄 | 区市町村の教育委員会 |
| 在籍学級 | 特別支援学級 |
| クラスごとの人数 | 8名 |
| 概要 | 小・中学校内にある障がいの種別ごとの少人数学級。 |
通級指導教室
普通学級に在籍しながら、障がいに応じた特別な教育を受けるために週に数時間のみ通う学級です。
| 対象 | 言語障がい、自閉症、情緒障がい、弱視、難聴、学習障がい(LD)、注意欠陥他動性障がい(ADHD)、肢体不自由、病弱・身体虚弱 |
|---|---|
| 管轄 | 区市町村の教育委員会 |
| 在籍学級 | 普通学級 |
| 概要 | 改善・克服に必要な指導を週1~8単位時間、特別な指導を受ける教室。 |
特別支援学校
障がいの程度が比較的重い児童生徒を対象として、専門性の高い教育を行う学校です。
| 対象 | 視覚障がい(視覚特別支援学校・旧盲学校)、聴覚障がい(聴覚特別支援学校・旧ろう学校)、知的障がい(知的障がい特別支援学校)、肢体不自由(肢体不自由特別支援学校)、病弱・身体虚弱(病弱特別支援学校) |
|---|---|
| 管轄 | 都道府県、区市町村 |
| 在籍学級 | 特別支援学校 |
| クラスごとの人数 | 平均3人 |
| 概要 | 障がいの程度が比較的重い子どもを対象として専門性の高い教育を行う学校。 幼稚園から高等学校に相当する年齢段階の教育を行う。 |
私立や大学付属の特別支援学校
障がい児教育に特化した私立小学校や教育大学附属の国立小学が全国各地にあります。
| 対象 | 学校ごとに異なる |
|---|---|
| 管轄 | 学校ごとに異なるが、在住自治体の教育委員会への教育相談は可能 |
| 在籍学級 | 在籍学校の学級 |
| クラスごとの人数 | 学校ごとに異なる |
| 運営 | 私立学校では、独自の教育方針から障がい児を含めた「混合教育」や「共同教育」を行う私立小学校が若干名の障がいのある児童の入学募集を行っている。 また、国立大学付属の小学校にも特別支援教育を行う学校があり、学校ごとに募集する障がいの種類や程度を規定している。 |
特別支援教育の見取り図
ここまで説明した公立小中学校での特別支援教育を図にすると、以下の見取り図になります。
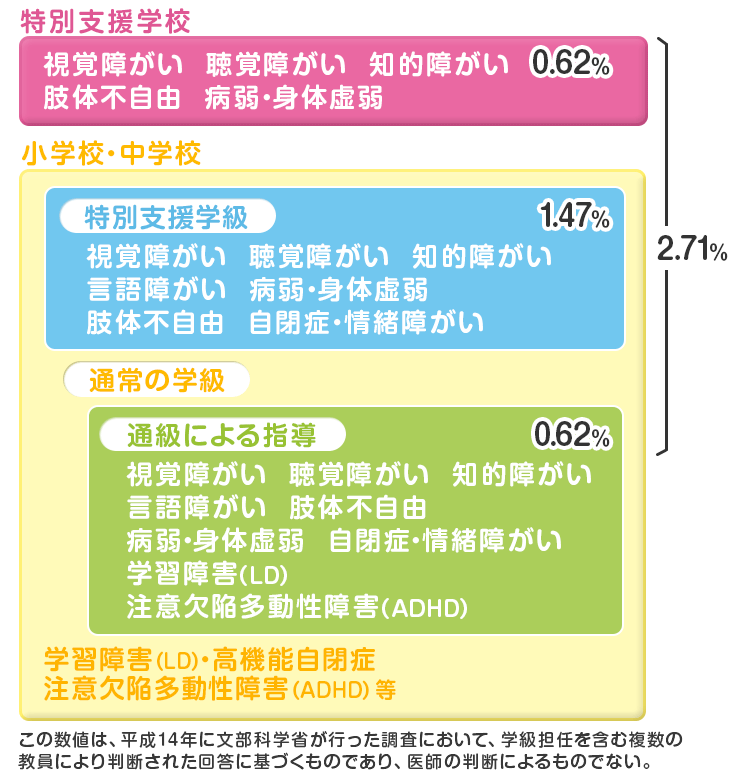
各学校は様々な関係機関とネットワークを作って、成長に応じた一貫した支援を行う体制を作っています。
発達障がい児の小学校教育に関わる教員・専門家とは?
発達障がいのお子さんに関わる小学校の先生・専門家の役割についてご説明します。

公務を管理して所属職員を監督する最高責任者。
校長を助け、公務を整理する職。
児童・生徒の養護をつかさどる教員。保健室の先生。
在籍する学級(普通学級・特別支援学級・特別支援学校内の学級)の担任。
特別支援学級に在籍する児童が、通常学級で交流・学習する際に在籍する学級の担任。
担任教師等と連携して、児童・生徒の日常生活上の介助(食事、排泄、教室の移動補助等)、学習支援、健康・安全確保、周囲の幼児児童生徒の障がい理解促進等の役割を担う。
各学校における特別支援教育の推進のため、校内委員会・校内研修の企画・運営や関係諸機関・学校との連絡調整、保護者からの相談窓口などの役割を担う。
不登校や問題行動を行う児童・生徒の悩みを受け止め、学校におけるカウンセリング機能や教育相談体制の充実を図る役割。心理臨床の専門的知識や経験を有するカウンセラー。
子どもの家庭環境による問題に対処するため、児童相談所と連携したり、教員を支援したりする福祉の専門知識や経験を有するソーシャルワーカー。
これらの関係者によって構成される「校内委員会」によって、全校的な支援体制を確立し、発達障がいを含む障がいのあるお子さんの実態把握や支援方策の検討が行われます。
みんなはどうしてますか?~先輩ママのお話
ここまでは【地域の差】【学校ごとの差】【先生の差】を抜きにした特別支援教育についてご説明しました。
しかし、学校選びに関して決め手となるのは、地域ごとの実情や先輩ママから聞く経験談ではないでしょうか。
3人のお母さんにお話を伺います。

Aさん:4歳のひとり娘の小学校進学に悩むお母さん。なんらかの広汎性発達障がいと医師に言われたが療育手帳はなし。月に数回療育センターに通っている。普通学級への就学を希望しているが不安も感じている。

Bさん:高機能自閉症の中3息子と、広汎性発達障がいの小6息子のお母さん。長男は普通級在籍で小4から通級へ通う。次男は普通級在籍で小1から通級に通う。

Cさん:アスペルガーとADHDの小4娘と、広汎性発達障がいの小3息子のお母さん。長女は普通学級在籍。長男は支援級在籍。

小学校選びって、就学相談票が届いてから動き始めるのでは遅いのでしょうか・・・?

年長さんの6月になったら就学相談票が届いて、市役所に出す。そこからスタートですよね。教育センターでの就学相談が夏~秋くらいで、その後は就学時検診。

今振り返ると、年長になればすぐに学校見学や就学相談に動けるようにしておきたかったかなぁ。年長の10月くらいには支援学級なのか通常学級なのか、通級教室に通うにしても手続きをする必要があるし...

親のエゴかもしれませんが、普通級で頑張って欲しいと思ってしまいます。

わかります。特別支援学校や特別支援学級を選ぶと、子どもに「障がい者」っていうレッテルを貼ってしまうような気がして、怖くなってしまいますよね。

普通級に通ってみて、もし辛くなったら支援級かなぁって思っていたけど、そんな簡単な話じゃないですよね。頑張りすぎたら学校に行きたくなくなるだろうし...

いろいろ考えてしまうけれど、結局、通うのは子どもなんですよね。親戚からの雑音もあったりしますが・・・。子どもにとっては何が一番いいのかを考えたいですよね。

私は近くの支援学級に在籍するお子さんの保護者の話が役に立ちました。あと、迷われている人は、まずはオープンスクールなどの機会に学校を見学することをオススメします。普通級も、支援級も、通級も、特別支援学校も。まずは見てくるのがいいと思います。

そうですよね。息子と一緒に行ってみて、学校のことを知ることも大事ですけど、学校に息子のことを知ってもらうことも大切だと思うんです。

見くらべたことで選ぶ基準を持てたりしますよ!

なるほど・・・。まずはオープンスクールに行ってみます。(緊張するから、パパにもついてきてもらおう・・・)
お母さんたちの話にもありました、学校選びに関して大切なのは「肝心の子どもにとって、どうなのか?」ということではないでしょうか。
「子どもの障がいのことで一番怖いのは二次障がい」という声もよく聞きます。
二次障がいは、周囲の無理解による不適切な環境が引き起こします。
学校選びに正解はありませんが、お子さんに合った学校選びを考える時に「見取り図」が一助となれば幸いです。
《関連する記事》
・発達障害とは? ~発達障害の定義・原因・種類・症状・相談窓口まとめ
・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(2015)『新訂版 特別支援教育の基礎・基本』ジアーズ教育新社
・青山新吾(2015)『今さら聞けない!特別支援教育Q&A』明治図書
・ブログ「うちの子流~発達障がいと生きる 発達障害を持つ子どもたちとの日々をつづります。」
・ブログ「発達障害児 トモの日常」
・文部科学省 特別支援教育について












