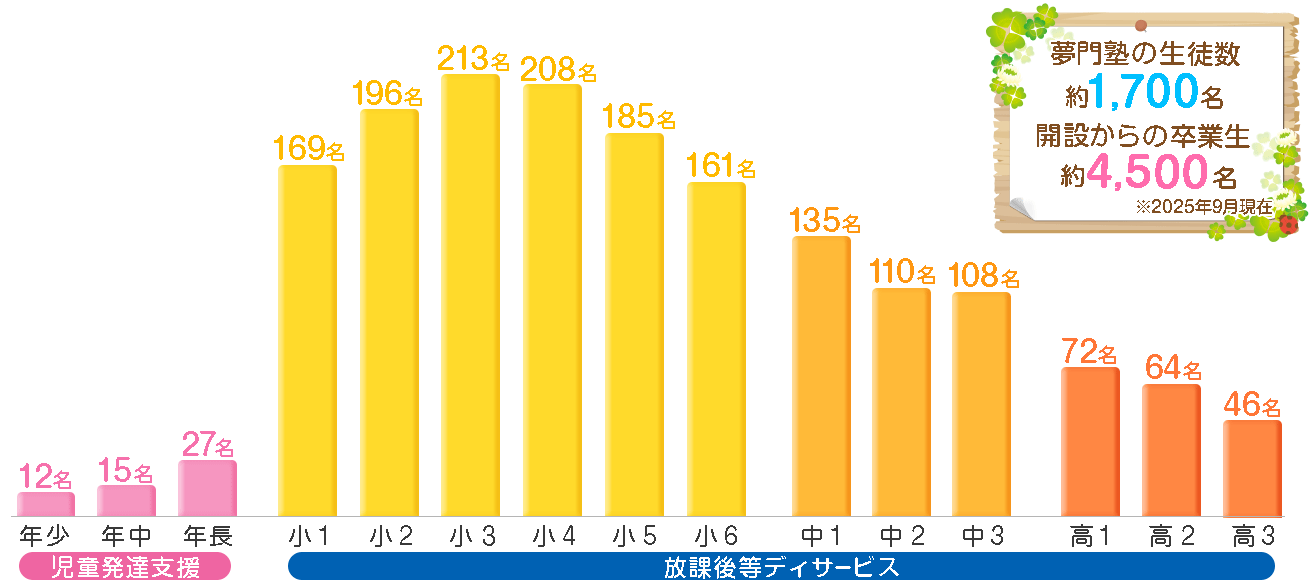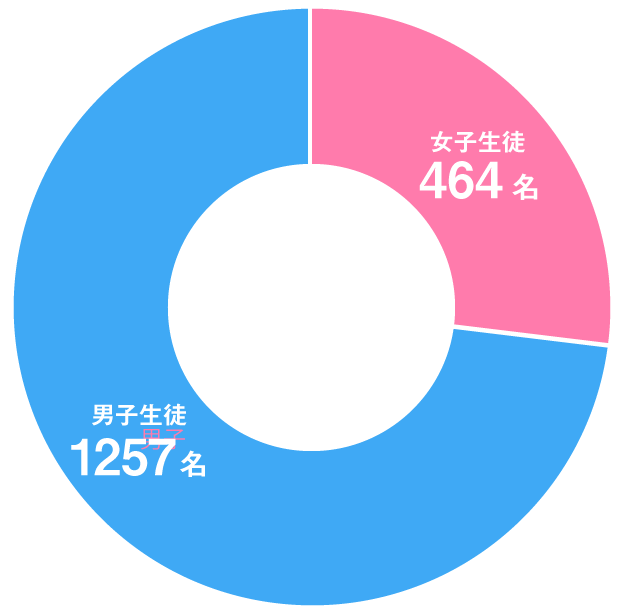| 2024.03.12 | 【神奈川エリア:白楽】施設見学会・発達支援説明会✨開催 |
|---|---|
| 2024.01.04 | 児童発達支援 夢門塾 戸塚原宿サービス廃止のお知らせ |
| 2023.12.14 | 慶應義塾大学SFC研究所との共同研究を開始します |

親だからこそ願う子どもの「生き抜く力」
人生を歩んでいく中で乗り越えていかなければならないことがある時
自分の力をたくましさに変えて挑戦し 乗り越えてほしい
願うご家族とともに 夢門塾で培う成功体験
夢門塾はご家族に寄り添いながらお子様の
「人生を生き抜く力」を育てる場所を目指します
夢門塾では、「運動」「学習」「生活」の3つのカリキュラムで
子ども達の発達支援を行っています

通所受給者証をお持ちの
小学生・中学生・高校生対象

通所受給者証をお持ちの
3~6歳の未就学児対象
見学に来てくださったご家族様から時々
「うちの子出来ないんですが…」「トイレも一人では…」「お箸が使えないんです。」
などとお聞きすることがあります。
夢門塾では、生活の基本的なことも大切にしています。
 ボタンを留める
ボタンを留める ランドセルをしまう
ランドセルをしまう 手洗い
手洗い 話を聞く
話を聞く 食事の挨拶
食事の挨拶 公共交通機関
公共交通機関